庭やベランダの彩りとして親しまれるガーデンチェアも、長年使用すれば劣化したり、模様替えで不要になったりするものです。
いざ処分しようと思っても、どのように進めれば良いのか迷う方も多いでしょう。
粗大ゴミとして出す、解体して一般ゴミにする、専門業者に依頼するなど、状況に応じた選択肢があります。
それぞれに費用や手間が異なり、素材や状態によっても最適な方法は変わってきます。
ここでは、ガーデンチェアをスムーズかつ賢く手放すための具体的な方法と、後悔しないための注意点について解説します。
ガーデンチェア処分の方法
粗大ゴミで出す
多くの自治体では、一定の大きさや重さを持つ家具を「粗大ゴミ」として収集しており、ガーデンチェアもこれに該当する場合が一般的です。
処分する際は、まず自治体のウェブサイトや広報誌で申し込み方法を確認し、事前予約を行います。
予約後、指定金額の「粗大ゴミ処理券」をコンビニや郵便局で購入し、受付番号を記入してチェアに貼り付け、指定日に搬出します。
費用は数百円程度で済むことが多く、比較的手軽な方法です。
ただし、申し込みから収集まで数週間かかることもあるため、計画的に進める必要があります。
一人で運べない場合は、家族や知人の協力を得ると安心です。
解体して一般ゴミで出す
ガーデンチェアを解体して素材ごとに分別し、一般ゴミとして処分することも可能です。
この方法は費用がほとんどかからない点が魅力ですが、解体作業には工具や時間が必要です。
金属製や頑丈な構造のチェアでは、安全な作業のために手袋を着用し、周囲を汚さないようシートを敷くなどの配慮も欠かせません。
分解後は、自治体のルールに従って燃えるゴミ、燃えないゴミ、プラスチック、金属などに仕分けて出します。
ただし、解体しても一定のサイズを超える場合は粗大ゴミ扱いとなることがあるため、事前の確認が必要です。
不用品回収業者に依頼する
不用品回収業者に依頼すれば、自宅まで回収に来てくれるため、搬出や分別の手間がかかりません。
複数のガーデンチェアや他の不用品をまとめて引き取ってもらえる点も便利です。
ただし、出張費や作業費などが加算されるため、費用は他の方法より高くなる傾向があります。。
また、自治体の許可を受けた正規の業者を選び、無許可の回収業者には注意しましょう。
ガーデンチェア処分で失敗しないための注意点
費用と手間を比較する
処分方法を選ぶ際は、「費用」と「手間」を比較することが重要です。
粗大ゴミは手数料が安い反面、申し込みや搬出の手間がかかります。
解体処分は費用がほぼゼロですが、作業に労力を要します。
業者依頼は最も手軽ですが費用が高くつくため、自身の状況に合ったバランスを見極めましょう。
素材や状態に合わせて判断する
ガーデンチェアの素材や劣化具合は、処分方法を決める上で大きなポイントです。
軽量なプラスチック製なら分解しやすく一般ゴミで出せますが、金属や木製の頑丈なものは粗大ゴミで処分する方が安全です。
壊れやすい場合や危険を伴う作業は無理せず、専門サービスを利用しましょう。
リサイクルや譲渡を検討する
まだ使用できるガーデンチェアは、リサイクルショップやフリマアプリへの出品も有効です。
必要とする人に再利用してもらえるだけでなく、処分費用を抑えられる場合もあります。
また、地域の掲示板や知人への譲渡も資源を無駄にしない選択です。
まとめ
ガーデンチェアの処分には、粗大ゴミ、解体処分、業者依頼、リサイクルなど複数の選択肢があります。
それぞれの費用や手間を比較し、自分の目的に合った方法を選ぶことで、効率的かつ安心して処分が行えます。
費用を抑えたいのか、早く処分したいのか、再利用したいのかを整理し、最適な手段を選ぶことが、賢く手放すための第一歩です。
投稿者プロフィール

- 不用品回収・買取アドバイザー
- 名古屋の不用品回収・買取サービス「クリーンスタッフ」で情報発信を担当しております。長年にわたり不用品回収業界に携わり、引っ越しや遺品整理、ゴミ屋敷清掃など、さまざまなケースに対応してまいりました。不用品の処分に関するお役立ち情報を発信し、お客様がスムーズかつお得にご利用いただけるよう努めております。また、環境負荷を減らすリサイクル・リユースにも力を入れ、持続可能な社会の実現を目指しております。
最新の投稿
 不用品回収コラム2026年1月5日家電リサイクル券の購入記入から正しい使い方まで処分方法別に解説
不用品回収コラム2026年1月5日家電リサイクル券の購入記入から正しい使い方まで処分方法別に解説 不用品回収コラム2026年1月1日不用品の買取対象品目を解説失敗しない業者選びのポイント
不用品回収コラム2026年1月1日不用品の買取対象品目を解説失敗しない業者選びのポイント 不用品回収コラム2025年12月28日遺品整理の費用相場はいくら?料金を抑えるポイントと悪徳業者対策
不用品回収コラム2025年12月28日遺品整理の費用相場はいくら?料金を抑えるポイントと悪徳業者対策 不用品回収コラム2025年12月24日引越し荷物処分に困らない賢い方法とスムーズな段取り
不用品回収コラム2025年12月24日引越し荷物処分に困らない賢い方法とスムーズな段取り

 対応エリア
対応エリア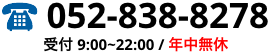
 サービス内容
サービス内容 不用品回収
不用品回収 料金
料金 選ばれる理由
選ばれる理由 作業実績
作業実績

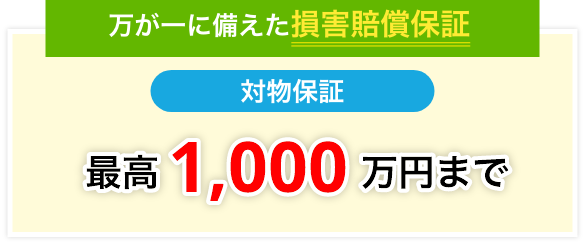
 無料お見積り
無料お見積り 感染予防対策について
感染予防対策について